10年以上にわたりドッグセラピストとして活動しているmamioが見たドッグセラピー体験談⑮は、活動性が低下して日中は部屋で寝ているため、昼夜逆転をしてしまっているKさんへのドッグセラピーのお話です。
この記事では、活動性が低下して昼夜逆転している認知症患者へのアプローチを、病棟スタッフと協力しながら行い、良い結果が得られた症例を紹介します。
はじめに

mamioは、病院、介護老人保健施設、障がい者支援施設などの複数の施設で、数千回のドッグセラピー活動経験を積んできました。
医師、看護師、作業療法士などと協力しながら行ってきたドッグセラピーの活動で、とても貴重な経験をさせてもらっていると思います。
コロナ渦にはドッグセラピーがほとんどできない状況も経験しましたが、現在は以前と同じようにふれあいセラピーができるようになりました。
ドッグセラピーの活動について調べていると
・犬と触れ合って笑顔が増えた
・無口だった方なのに、話す言葉が増えた
・精神的に安定した
などの、効果について、頻繁に目にします。
ドッグセラピーに興味のある人なら「なんとなくドッグセラピーはいいものなんだろうな~」「犬がいると癒されるよね」と感じてくれると思います。
それは、とても嬉しいことなのですが、個人的には、ちょっと物足りなく感じることが多いです。
これだけではよく分からないな~、もっと詳しく知りたいな~、と感じることが多いです。
もしかしたら、私と同じように感じている人もいるのでは?と思い、まずは自分の体験について書いてみようと思いました。
もっと多くの人に、ドッグセラピーの現場を知って、興味をもってもらいたいです。
体験談⑮ 昼夜逆転しているKさんへのドッグセラピーのお話

体験談⑮は、日中は部屋にベッドで寝て、夜になると病棟を歩き回る生活をしている、昼夜逆転してしまったKさんへのドッグセラピーのお話です。
ご飯の時間に声をかければ部屋から出てきて、決まった量をしっかり食べられてはいましたが、食べ終わると部屋に戻って横になる生活を繰り返していました。
そんなKさんに対して、ドッグセラピーによるアプローチを検討しました。
Kさんのこと
Kさんは仕事を退職してから飲酒量が増え、数か月後には短期記憶の低下などの症状が現れ始めました。
その後もアルコール多飲に加え記憶力低下などの認知症状がすすみ、自宅介護困難となり入院されてきました。
生活に必要である、食事、入力、排泄などの行為は問題なく行えてはいましたが、それ以外の時間のほとんどを部屋で過ごしていました。
意欲が低下し、レクリエーションなどの活動にも参加せず部屋での時間を好んでいました。
日中に部屋で過ごすこと自体は問題ないのですが、常に横になって寝てしまっているため、夜間になると目が覚めて病棟を歩き続けてしまう行動が出てきてしまいました。
部屋に戻るように声をかければ、すぐに戻りますが、短期記憶力が低下しているために、数分後には再び病棟を歩き回っていました。
時間・場所・人への見当識が著しく低下しているのに加え、昼夜逆転、感情の表出が乏しい様子が確認されていました。
Kさんの関心のあるもの
セラピストが病棟を訪れた際、Kさんが食事の時間が近くなってきたために部屋から出てきてホールの椅子に腰をかけていました。
セラピー犬を見つけたKさんが犬に片手を伸ばしていたので、ドッグセラピーでの介入も可能なのではないかと考えました。
ただ、Kさんについては病棟のスタッフや他職種で個別に関わる治療は実施されていなかったため、Kさんに関する情報が乏しい状況でした。
Kさんに活動を提供するにあたり、まずはKさんが関心の高いものは何か確認するところから始めようと思い、その場で関心事項を質問してみることにしました。
Kさんは短期記憶は低下していましたが、自身の好きな物は問題なく伝えることができます。
自らセラピー犬に手を伸ばしていたので近くまで行くと、微笑みながら犬の体を撫で始めたので、犬に対する抵抗感はなく、むしろ好意的であることが分かりました。
また、園芸への興味が比較的高いことが会話から読み取れました。
その他、普段の様子から巧緻性に優れていたので、創作活動の導入も可能ではないかと考えました。
Kさんとドッグセラピー

これまで、Kさんはほとんどの時間を部屋のベッドで過ごしていたため、セラピー犬との接点はありませんでした。
夜間帯はKさんはホールで過ごすことも多かったのですが、セラピー犬は日中のみ活動しています。
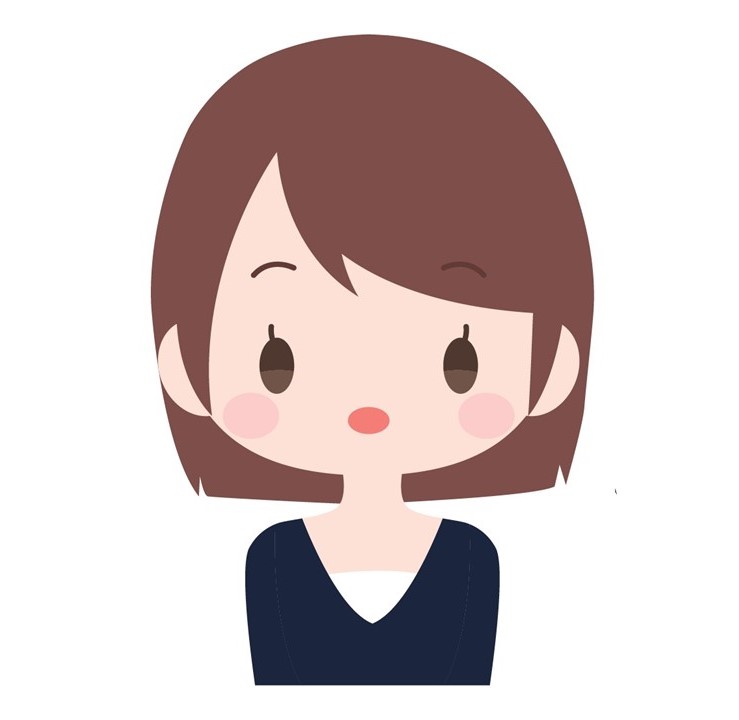
夜間の業務、残業などで、セラピー犬の体への負担が大きくなることは避けます。
Kさんについての情報が少ないため、手探り状態で交流をスタートします。
園芸活動
Kさんが認知症になる前の余暇活動として、最も興味がありそうなのが「園芸」であることは事前に聴取していました。
病棟のベランダには園芸活動ができる場所が設置されていたので、そこで簡単な園芸作業を行うことにしました。
意欲低下があるため、主体的に何か作業を行うのは難しく、お手伝いをしていただく形で鉢植えへの水やりからスタートしました。
作業を始めてしまえば、全部の鉢に水をあげるまできっちりこなせますし、雑草を抜いたり、花がらを摘んだり、自発的な行動があらわれました。
ベランダに出ることで屋外の気候を感じることができるので、時間の見当識が低下しているKさんにとっては季節を確認する良い時間になっていました。
また、昼夜逆転の生活を基に戻すことに対しても効果が期待されます。
園芸活動とセラピー犬
Kさんに園芸活動を提供するだけなら、セラピー犬は必要ないのでは?と思うかもしれません。
確かに、セラピー犬がいない状態で園芸活動を提供しても、生活リズムを修正することは可能です。
Kさんの場合、作業を始めてしまえばスムーズに実施できるのですが、ベランダまで移動することがネックになっていました。
そこで、きっかけ作りとしてセラピー犬の存在を活用していました。
「セラピー犬が歩きたがっているから散歩のために部屋から出て歩き、セラピー犬が外に行きたがるのでベランダに出る」といった形に設定しました。
自分のための行動は面倒くさくてやりたがらないけれど、誰かのためなら行動しよう、という元々の優しい性格に合わせて、活動提供方法を設定しました。
数回に一度は拒否されることもありましたが、おおむね活動を提供することに成功していました。
短期記憶力の乏しいKさんではありましたが、繰り返し実施することで、「犬が来たからベッドから起きる」という行動が定着しました。
このようにセラピー犬をシンボル的に活用するのも、ドッグセラピーの方法の1つです。
活動の場を広げる
ベランダでの園芸活動がスムーズに行えるようになったところで、さらに活動量を増やすことを検討しました。
体力的には問題がないため、園芸活動の場をベランダから病院の中庭にうつしてみることにしました。
場所の移動が入り、鉢植えから畑に園芸作業場所が変更することで、日中の活動量が大きくなります。
それにより、夜の睡眠時間を長くして昼夜逆転の生活を、より直していく狙いがあります。
畑の準備には病院の管理職員に協力をしてもらい、万全の体制を整えました。
畑までの移動の際は、Kさんにセラピー犬のリードを持っていただき、実際に散歩をしながら畑に向かったところ、歩行中はセラピー犬をよく見て配慮しながら歩く様子がみられていました。
途中、ソファに腰かけセラピー犬とのふれあいを楽しみながら表情、感情の表出豊かに過ごすことができました。
集団での活動
個別に中庭で園芸作業を行うことに問題ないことが確認できたので、今度は4~5人の小集団での活動を行うことにしました。
ドッグセラピスト1人ではフォローしきれない人数になったため、作業療法士と協力して活動を行いました。
他患者が率先して作業を行う中、Kさんは後方に立ち見守っていましたが、促すことで作業を開始できました。
巧緻性に優れ、小さい雑草の除去や種まきを集中して行いました。
種まきの際、他患者に種を譲ろうとする配慮がみられ、協調性の向上も確認することができました。
また、園芸作業後も他患者とセラピー犬を撫でながら、ゆっくり活動を継続することができました。
Kさんへのドッグセラピーの効果
日中、部屋のベッドで寝ている生活をしていたために昼夜逆転してしまっていたKさんでしたが、活動を提供することで生活リズムを整えることができました。
セラピー犬は園芸活動のきっかけを与える存在として導入しましたが、園芸活動終了後もセラピー犬を通して他社との交流が広がっていきました。
また、創作活動などの他の活動にも参加する機会を増やすことができました。
さいごに

体験談⑮は、昼夜逆転しているKさんへのドッグセラピーのお話です。
この症例では、ドッグセラピストがKさんの生活背景や関心事項を調査しながら活動を始め、状況に応じて他職員と協力して実施する形をとりました。
生活リズムを整えるという明確な目標に向けて、Kさんの興味のある活動を設定できたことで、短期間で良い結果を得ることができました。
ドッグセラピーだけの活動にこだわらず、様々な良い活動と組み合わせることで、シナジー効果が得られた良い症例です。


