施設や病院、教育機関など、多くの場所で日々レクリエーションが開催されています。
集団に対して行うレクリエーションは、多くの人に活動の場を提供することができることもあり、なくてはならない活動の一つと言っても過言ではないでしょう。
レクリエーションは、ドッグセラピー(動物介在療法/動物介在活動)においても多く取り入れられている活動です。
今回の記事では、セラピー犬と一緒に行うレクリエーション『ドッグレクリエーション』について紹介します。
レクリエーションについて
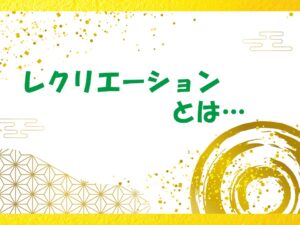
ドッグセラピーを集団で行う際には、レクリエーションの形で行うことも少なくありません。
そこで、ドッグセラピーにおけるレクリエーションについて、簡単に紹介したいと思いますが、そもそも「レクリエーションって何?」と思われた方のために、レクリエーションについて説明します。
それは知ってるよ!という方は読み飛ばしてくださいね。
レクリエーションの目的
レクリエーションとは、娯楽として行われる活動のことで、楽しいひと時を過ごせるように、心身をリラックスさせたり、ストレス解消などを目的として行われています。
学校などで子供たち向けに実施されることもありますし、高齢者施設では入所者向けに実施されています。
介護施設などで行われる高齢者向けのレクリエーションは、入所されている複数の方に同時に提供される、集団でのレクリエーションが頻繁に行われていて、体操、クイズ、カラオケなど様々な内容があります。
ADLが保たれている自立した利用者から、寝たきりの方まで、現場では多くの方に楽しんでもらえる活動が提供されていますが、レクリエーションには楽しみの提供以外にも大事な役割があります。
①身体機能の維持・向上
立つ、歩く、座るといった生活に必要不可欠な動作を行うためにも、筋力を維持する必要があります。
施設などに入居していると、料理や掃除など、日常的に行っていた家事も行わなくなり、外に散歩に行くことも自由にできないでしょう。
その中で必要な筋力を維持することは、よほど意識して身体を動かさなければ難しいのではないでしょうか。
そこで、レクリエーションで身体機能の維持・向上をさせるための運動を行います。
②認知機能の維持・向上
高齢になると、記憶力や理解力など、認知機能の低下がみられるようになり、何も対策をしないと脳の萎縮がどんどん進んでしまいます。
記憶・学習などの能力を維持させるためには、脳トレを取り入れると効果的です。
また、適度に身体を動かすことで脳を活性化させることも、合わせて行いたい活動です。
脳を活性化させるための脳トレや運動を取り入れることで、認知症の予防や進行を遅らせる効果があります。
③コミュニケーションの促進
高齢になると身体機能が低下し、意欲も低下しやすくなっているため、他者とのコミュニケーション能力は低下しやすくなっています。
おまけに、施設などに入居していると、昔からの知り合いはおらず、知らない人ばかりがいる環境に身を置くことになるので、余計に他者との関りが薄くなる傾向があります。
孤独を感じると精神的な落ち込みもあり、意欲が低下して身体を動かす機会が減るなど、様々な影響があります。
施設の職員だけでなく、他の利用者とも交流をすることで楽しさを感じられると、認知症の予防にもつながります。
④生活の質の向上
日常に必要な動作をする能力を保つこと(ADLの向上)は、その方の生活の質の向上にもつながります。
その人らしさを大切にした生活を送れることはとても大切で、充実感や満足感を感じられるように心身機能を維持できるようにレクリエーションを行う必要があります。
レクリエーションの種類
ここまでで、レクリエーションを行うことで得られる効果が、楽しみの提供だけではないことを説明しました。
数十人が一度に参加する大集団でのレクリエーションにはクイズなど様々な種類がありますが、他にもたくさんあります。
レクリエーションにもバリエーションがないと、毎日同じ活動しかできず、参加する方も飽きてしまいますよね。
利用者に「参加したい」と思ってもらえるような内容にするためにも、提供するレクリエーションに多くの種類があると好ましいです。
運動プログラム

「運動プログラム」と大きなくくりで書きましたが、体を動かせる内容全般のことです。
10月になると恒例の運動会を実施する施設も多いのではないでしょうか。
具体的な運動の内容は、風船バレーボール、ボーリング、綱引き、玉送りなどの種目があります。
例えば、大きな風船を使った「風船バレーボール」であれば、一度に大勢の方が参加できますし、ボールの代わりに風船を使うことで当たっても怪我もしないので安全です。また、球速も落ちるので反応しやすくなります。
ただし、稀に風船が割れることもあり、音が大きくてびっくりします(笑)
音楽プログラム

音楽があるだけで、その場の雰囲気を作ることができるので、万能プログラムといっても過言ではありませんね。
参加されている方の好みに合わせたり、かつて流行っていた曲を選ぶことで、より音楽による効果を引き出すこともできます。
カラオケ、イントロゲームなどとして音楽を使ったり、楽器演奏と組み合わせることもできます。
創作プログラム

塗り絵や折り紙などを用いて作品を完成させる創作プログラムは、小集団から大集団まで取り組みやすいです。
完成した作品を展示することで、レクリエーションが終わった後も、参加者の達成感、満足感につながります。
大集団でも創作活動は、参加される方の身体レベルによってはフォローの手が必要となります。
マンパワーを考慮しながら、プログラムを選ぶと良いでしょう。

mamioはお正月に習字のレクリエーションをしたことがありますが、参加された皆さんが達筆で、完成品を壁に掲示すると大変喜んでいただけました。
ドッグレクリエーション

体操、音楽など様々なレクリエーションの種類がありますが、セラピー犬を主としたプログラム『ドッグレクリエーション』もまた、レクリエーションの仲間の1つです。
セラピー犬が参加するだけでも、「参加者の笑顔が増えた」と言ってもらうこともありますが、プログラムの内容が薄ければ、参加者の心身の支えとしては効果が低くなってしまいます。
他のプログラム同様、セラピー犬で何をするか?がとても大切なカギとなってきます。
プログラムの構成
セラピー犬が大きく動けば見栄えは良いかもしれませんが、動き続けるプログラムでは体力が持ちません。
疲れているセラピー犬を見ても利用者に「かわいそう」と思わせてしまいますし、大事なパートナーであるセラピー犬に大きな負担はかけたくないですよね。
参加者の安全を考慮するのと同時に、セラピー犬への負担軽減も考慮しながらプログラムを設定していきます。
犬の動きのあるダイナミックで動的なプログラムと、じっくり考えて行うような静的なプログラムを組み合わせて、プログラムが単調にならないように構成を決めていくと良いでしょう。
動的なプログラム
セラピー犬の動きを使った動的なプログラムは、見栄えがして参加者の反応が良いです。
様々なプログラムがありますが、下記のようなものが取り入れやすいです。
・一芸披露
・徒競走
・早食い競争
一芸披露は、1頭でも行えるので便利なプログラムです。得意としている技を選ぶと本番で安心して取り組めます。
徒競走は、会場の広さや参加者によって二足歩行にして実施すると、見やすくなることもあります。
どのプログラムも、セラピー犬が興奮してどこかへ行ってしまわないように、しっかりコントロールできるようにしておきましょう。
構成を考えるにあたり、まずセラピー犬のできることが何かを把握しておく必要があります。
特に、一芸披露など日ごろからトレーニングしていないとできないことは、いつもと違う環境でも成功できる安定した技を取り入れたいところです。
静的なプログラム
参加者もじっくり考えながら落ち着いて参加できるプログラムで、セラピー犬だけでなく参加者にとっても必要な時間となります。
・クイズ
・セラピー犬のマテ競争
・衣装披露
クイズは脳トレの要素をドッグレクに取り入れることができます。
セラピー犬の見た目の印象で予想してもらうクイズはもちろん、代表者に抱っこをしてもらって体重を当ててもらうこともできます。
また、犬の食嗜好を活用して、特定の食べ物について食べるかどうかのクイズを出すこともできます。
食べるか?クイズの場合は、セラピー犬が食品に反応を示す様子を見て予想してもらえれば、適度な犬の動きも楽しめるので、動的と静的の中間の要素があります。
衣装披露では参加者の好みに合わせて準備したり、季節に合わせた衣装を準備すると良いでしょう。
特に認知症の方などは、時間の感覚が失われていることもあるので、季節感の分かる衣装を提示することは認知機能の向上という意味でも良い効果があります。
夏場に浴衣を取り入れるメリットについて記載した記事はコチラです。
気をつけたいこと

どのレクリエーションでも、集団でも安全への注意は必要となりますが、セラピー犬が入ることで特に気をつけないといけないことは、犬の好き嫌いやアレルギーです。
これらについては事前に確認を行い、座席の配置の参考にするとスムーズに進行できるでしょう。
また、動物アレルギーについては慎重に対応する必要があり、症状の重さによってはドッグレクへの参加は難しいという判断も必要となります。
それから、セラピー犬への負担についても慎重に考えてプログラムの構成を考える必要があります。
レクリエーションは60分ほどの時間で構成されることが多いと思いますが、その時間いっぱいセラピー犬が集団の前に出ていることになります。
普段とは違う環境でストレスを感じる中で、セラピストの指示の通りに動くのは、セラピー犬にとって大変な作業となります。
動的プログラムと静的プログラムを組み合わせつつ、自身のパートナー犬に過度の負担がかからない項目を取り入れるように検討してみてください。
参加者もセラピー犬も、そしてセラピストも楽しいと思えるレクリエーションを目指して、活動していきたいですね。
ドッグレクリエーションのサポート役についての記事はコチラにあります。




