10年以上にわたりドッグセラピストとして活動しているmamioは、現場で様々な体験をしてきました。
ドッグセラピー体験談⑬は、病気の影響で体が自由に動かなくなっていきつつあるMさんへのドッグセラピーについて書いていきます。
この記事では、定期訪問ではなく、毎日関わる個別ドッグセラピーを行うからこそ提供できた、Mさんへの特別プログラムを紹介します。
はじめに
mamioは、これまでに10年以上にわたり、病院、介護老人保健施設、障害者支援施設などで、数千回のドッグセラピー活動経験を積んできました。
医師、看護師、作業療法士など多職種と協力しながら行ってきたドッグセラピーの活動で、とても貴重な経験をさせてもらっていると思います。
ドッグセラピーの活動について調べていると、抽象的な表現を多く目にします。
「犬と触れ合って笑顔が増えた」、「無口だった方なのに、話す言葉が増えた」、「精神的に安定した」
どの言葉も、ドッグセラピーによって良い効果が得られたことは分かります。
ですが、「犬に触れ合って」といっても、どのように触れ合ったのかはよく分からないことが多いのではないでしょうか。
もう少し具体的にドッグセラピーの様子を伝えてみたいと思い、まずは自分の体験について書いてみようと思いました。
この記事を読んでいただき、ドッグセラピーに興味をもってもらえたら嬉しいです。
体験談⑬ 毎日実施できるからこそできるドッグセラピーの話

体験談⑬は、病気の影響で体を自由に動かせなくなってしまい、活動を制限されてしまったMさんへのドッグセラピーのおはなしです。
Mさんのこと
Mさんは80歳代でパーキンソン病の影響により、身体が自由に動かすことができないために入院生活を送っていました。
Mさんご本人からもお話は聞いていましたが、ご家族からの情報によると、元々、非常に活動的な方だったそうで、家族や友人たちとの旅行がとてもお好きでした。
その他にも、ダンス、琴の演奏、カラオケ、手芸など、趣味も多い方で、人前に出て何かされることが得意で、友好的な性格から周囲の人間とコミュニケーションをとることを好まれていました。
Mさんは入退院を繰り返していたのですが、交流は10年ほどの長い期間に及びました。
Mさんとのドッグセラピー

先ほど述べたように、入退院を繰り替えしていたMさんとの交流期間は、約10年に渡ります。
その間に病気が進行して行動を制限されていく中、ドッグセラピーを通してMさんに楽しい感情を少しでも増やしていただけるような関りになるように活動していました。
交流初期
Mさんに初めてお会いした時は、まだ歩行器を使用して移動することが可能な状態でした。
他の患者さんとは違い、入院中でも身だしなみを整えて毎日綺麗にお化粧されていました。
表情も明るく、ご自宅から持参された雑誌を読んだり、率先してマイクを握ってカラオケのレクリエーションに参加されていました。
他の患者さんへの世話役も買って出てくださり、入院して間もない患者さんがいれば、1日のスケジュールを教えてあげたり、塗り絵など自由に使用できる道具を持ってきて、活動を提供してあげる様子もみられました。
セラピー犬に対しても非常に友好的で、複数頭いるセラピー犬に対して、平等に可愛がってくださる様子がみられました。
mamioの病院では、セラピー犬と触れ合った記念に写真撮影を行い、プレゼントをしていました。
Mさんは写真撮影が大好きで、「ここで撮った方がきれいじゃない?」と撮影背景にも素敵なアドバイスをしていただけることが多かったです。

写真撮影をより楽しんでいただくために、病棟の中だけではなく、中庭やロビーに飾られているお花など、様々なシチュエーションで撮影できるように工夫をしていましたよ。
歩行器で移動する時にはセラピー犬のリードを持っていただいて一緒にお散歩を楽しみ、移動した後は近くの椅子に腰をかけ、セラピー犬が隣に座った状態、または膝の上に抱っこした状態での撮影を楽しまれていました。
セラピー犬の頭や背中を掌全体で優しく撫でながら、セラピストとの会話も楽しまれていました。
交流中期
病気の進行により、歩行が難しくなってきてしまったMさんですが、車いすで移動し、前向きで明るい表情を気丈にたくさん見せてくれていました。
以前同様、日々のスキンケアや化粧も欠かさず、様々な活動に積極的な姿勢がみられていました。
元々世話好きなMさんなので、他の入院患者さんのことを気にかける様子も頻繁にありましたが、車いす生活のため自由に行動することができないため、他の人に依頼をすることでお世話をできていましたが、自らの手で行えずに、もどかしい思いをされていたと思います。
カラオケ、塗り絵、創作などの活動には積極的に参加されていましたし、周囲の方とのコミュニケーションも良好に過ごされていました。
数年前と比べると、手も足も自由に動かすことが難しくなっていますが、Mさんの中で気持ちの折り合いをうまくつけて過ごすことができていることが、とても尊敬できると思いました。
ドッグセラピーを通してMさんにプラスになることは何かないかと考え、「お世話をする」ことを提供することにしました。
お世話の内容は、セラピー犬への「トレーニング」に挑戦です!
Mさんは、普段からドッグセラピストがセラピー犬たちのトレーニングをしていることをご存知だったので、新しい技を教えることに意欲的になりました。
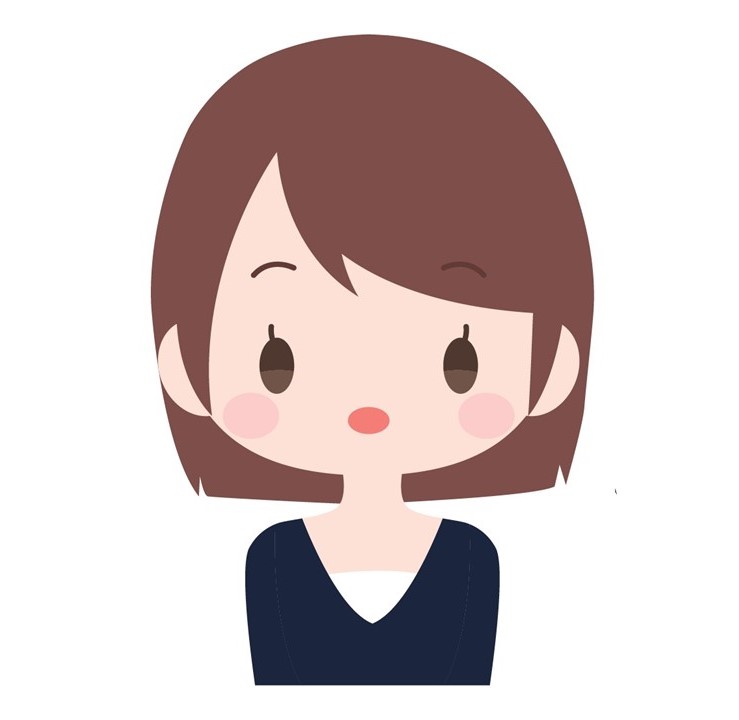
犬のお世話といっても、おやつあげは以前から実施していましたし、ブラッシングや歯磨きなどのお世話は衛生面の問題で実施は難しいと判断しました。
セラピー犬とのトレーニング

セラピー犬とMさんとのトレーニングの時間を作って挑戦したトレーニングは、『楽器演奏』です。
歌に合わせてタイミング良くカスタネットを叩く技を、セラピー犬に教えることにしました。
高齢の方は、セラピー犬に「お手」と自身の掌を差し出す行動をする方が多く、かつて飼い犬とお手をして遊んで過ごされていたのだろうな、と連想する機会が頻繁にありました。
そこで、カスタネットを置いた掌を犬に向け、「お手」をするのと同じようにカスタネットを叩いて演奏するように設定しました。
セラピー犬がカスタネットを叩いて音を出せるようになるまでは、あまり時間がかかりませんでした。
大事なのは、タイミング良く叩くことです。
タイミング良く叩くには、タイミング良く叩くように指示を出す必要があります。
Mさんが指示を出してから、どれくらいの間隔を置いてセラピー犬がカスタネットを叩けるか?
差し出す掌の角度によってはセラピー犬が良い音を出せないこともあるので、どんな角度が好ましいか?
そのようなことを2週間ほど繰り返し練習して完成したのが「幸せなら手をたたこう」です。
発表会
歌が好きで、人前で何か発表することに抵抗のないMさんでしたので、セラピー犬にトレーニングを行い完成した「幸せなら手をたたこう」の完成披露発表会を行うことにしました。
多くの患者さんが集まるレクリエーションの時間の中に、Mさんの発表時間を設定しました。
この発表機会の調整には、普段からMさんの入院病棟を担当している作業療法士さんに協力していただきました。
Mさんや他の患者さんのことも良く知る作業療法士さんなので、過度に緊張することのないように、うまく進行してくださり、他の患者さんからの温かい応援の眼差しをの中で発表できました。
みんなの注目を浴びて行った発表会。
結果は、大成功です!
演奏を終えたMさんとセラピー犬には、見守ってくれた皆様の優しい笑顔と温かい拍手が送られました。
今回の挑戦によって、新しいことに挑戦し成功をおさめ、それを多くの方に祝福されることで、Mさんの自己肯定感を増すことに繋げられました。
交流後期

一緒にカスタネットの演奏をしてから数年ほど経過した頃、車いすに長時間乗っていると、お尻に褥瘡ができてしまうため、Mさんは多くの時間をベッド上で過ごしていました。
以前のように大きな声もでなくなり、かすれた声で発言されるので、車いすに乗車している時でも他の方とのコミュニケーションも難しくなっていましたが、まだ様々なことをやりたい気持ちは変わらず持っていました。
そんなMさんが希望されたのは、セラピー犬のポンチョを編むことでした。
最初は、認知症患者がいる病棟のため、ご自身で道具の管理が難しいMさんに編み物の提供は難しいという意見がありました。
それでも、「誰かのために何かをしたい」というMさんの思いや、かつては子供や孫のために編み物をしていたこともあり、その頃を懐かしんでいただきたいという気持ちから、病棟を説得しました。
その結果、ベッドサイドに常に編み物道具を置いておくことは危険だが、決めた時間のみ見守りしながら編み物をするのであれば良い、という条件付きの了承が得られました。
もちろんMさんの体調が最優先なので、体調が悪く編み物ができない日もありましたが、ドッグセラピストがMさんの元に編み物道具一式を持参して活動を提供しました。
イメージが湧きやすいように、セラピー犬が傍にいて、好きな音楽を聴きながら編み物を続けていただきました。
1か月ほど続けていると、編み物の時間の提供は、病棟の看護師さんも協力をしてくれるようになりました。
セラピー犬の勤務時間は日勤帯のみに限定されていたため、夕食後などの時間帯にドッグセラピストが提供することはできないので、病棟のスタッフがMさんの希望に合わせて提供をしてくれていました。
時には、Mさんと看護師さんで「あの子に似合うのはこっちの色かな?」と相談をして毛糸を選ぶこともあったそうです。
3か月ほどの時間をかけて、セラピー犬のポンチョは完成しました。
女の子のセラピー犬ということもあり、薄いピンクを基調とした優しい色合いのポンチョで、ひとつずつ丁寧に編まれた大切な贈り物となりました。
ポンチョを身に着けたセラピー犬が病棟をまわり、皆さんに衣装披露をすることでMさんへのフィードバックを行うことができました。
日常的にドッグセラピーを行えること

Mさんへのドッグセラピーについて、病気の進行状態に合わせ、前期、中期、後期の3つの時期に分けて紹介してきました。
それぞれに違う活動を提供していますが、全てに共通しているのが、常にドッグセラピーを提供できる体制になっていることです。
中期の楽器演奏は連日練習を行うことで、しっかりと発表できるほどの完成度に高めることができました。
そして後期については、Mさんの体調に合わせての活動提供のため、常にMさんの近くに行かれる体制があったので実施できました。
そして、常に病棟に出入りしているドッグセラピストなので、作業療法士や看護師との連携も可能となり、質の高い活動に繋げることもできました。
この体験談⑬で紹介した内容は、日常的にドッグセラピーを行っているからこそ行えることのできたセラピー活動です。
他職種の協力の元で行うことのできたドッグセラピーについては、コチラの記事でも紹介しています。
さいごに

ドッグセラピー体験談⑬では、病気の影響で体を自由に動かせなくなってしまい、活動を制限されてしまったMさんへのドッグセラピーについて紹介しました。
様々な物事に対して意欲的なMさんの気持ちを大事にして、その時にできる内容を選んで活動を提供しました。
ドッグセラピーでなくても提供できる活動はたくさんあります。
セラピー犬がいるからこそ、挑戦してみたくなる活動に焦点を当てて取り組むことで、Mさんの生活を豊かにすることができたのではないでしょうか。
そして、それができたのも、日常的にドッグセラピーを行っていたからこそです。
定期訪問でのドッグセラピー活動にも良い点はたくさんありますが、日常的に行うドッグセラピーならではの良さもたくさんあります。
もっと日本で日常的なドッグセラピー活動が増えると、ドッグセラピーの可能性が広がっていくのではないでしょうか。



